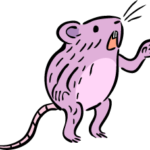
生命保険加入時に公的保障のことは一切聞いてない!

節約できるかも。。。
公的保障を知ればコスパの良い保険が選べます。
公的保障を知らないと無駄に保険料を払っている可能性大です。
保障や保険と名のつくものには3つに分類できます。
- 公的保障
- 企業保障
- 私的保障
生命保険は、公的保障で足りない部分を入れば問題ありません。
この記事を読むことで、公的保障の種類、給付金額がわかるようになります。
10分知識をつけることができ、保険選びでの失敗せずコスパの良い保険選びができるようになります。
公的保障でカバーできるリスク
これらはリスクです。公的保障で金銭的に助かる仕組みがありますが、最低限の保障であり、十分な保障ではありません。
死亡
世帯主が亡くなると収入が途絶えます。今後の生活費など様々なことに支障が出ます。
介護状態
介護費用、介護施設費用、リフォーム費用などの出費が増えます。また誰が介護をするのかという問題も。
障害状態
障害状態は継続します。障害の程度によっては、仕事の選択肢が減ってしまう恐れもあります。
就業不能状態
働くことができない状態です。収入が減ってしまい家計が崩れます。
病気・けが
入院や手術時に費用が発生します。個室に入ると差額ベッド代がかかり、さらに家族のお見舞い費用(交通費など)や外食代の発生。
現在、記事を編集中。近日公開予定

これらのリスクに対して国や企業が準備をしているものがあります。
会社員と自営業者では保障が違う
公的保障は、さまざまな制度があります。
会社員は手厚く、自営業は手薄いか、保障がありません。
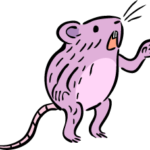
自営業者は保障が少ないのか。。

払っている保険料がそもそも違うんだよね。
【死亡リスク】には【遺族年金】
死亡のリスクに対しては遺族年金が受けられます。
遺族年金が受けられるのは、家庭を持っている人です。独身の人が亡くなっても、家族への保障は基本的にはありません。
ざっくり遺族年金の仕組み
遺族基礎年金
会社員・自営業 どちらもあり
遺族の人数によって給付額が違います。
78万1700円+子の加算額(22万4900円×2人)
合計は約120万/年(月だと10万)
78万1700円+子の加算額(22万4900円×2人、7万5000円)
※子供3人目以降は7万5000円の加算
合計は約130万/年(月だと10万ちょっと)
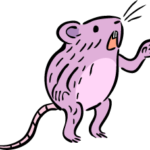
遺族基礎年金は子供の人数によって変わるんだね
- 配偶者・子供1人 約100万
- 配偶者・子供2人 約120万(月10万)
- 配偶者・子供3人 約130万
- 配偶者・子供4人 約140万
- 配偶者・子供5人 約150万(月12.5万)
※18歳までを子供としてカウントします。
遺族厚生年金
会社員のみ
遺族厚生年金は会社員の遺族が受け取れます。
遺族厚生年金の額は、老齢厚生年金の報酬比例部分を計算した額の4分の3に相当する額です。
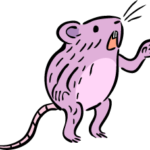
いきなり意味わからん!

ざっくり計算できるからご安心を。
遺族厚生年金は、年収の10分の1です。
年収300万なら30万
年収400万なら40万
年収500万なら50万
年収600万なら60万
年収700万なら70万
年収800万なら80万 こんな感じです。
会社員の方は、遺族基礎年金も受給できるので両方を合計した金額になります。
自営業者は遺族基礎年金のみ、会社員は遺族厚生年金が上乗せ
例えば、年収500万の3人家族の場合・・
- 遺族基礎年金は120万
- 遺族厚生年金は50万 なので
遺族年金として170万を毎年受け取れます。
遺族年金で家族の保障はある程度されています。

会社員の家族でも、月にすると10万ちょっと。生活できないかもなぁ。
★コスパ★配偶者に収入あれば保障は不要
配偶者が働いていると、収入源は遺族年金と配偶者収入の2つになります。収入によりますが、生命保険で死亡保障を備える必要がない場合もあります。
配偶者の収入を考慮せずに加入した生命保険はコスパ可能性ありです。
実際には必要ない高額の保障に加入しているかもしれません。配偶者の収入と遺族年金で生活できる人は、世帯主に大きな死亡保障は必要ありません。
子供が2人で年収600万の夫が死亡した場合の遺族年金はざっくり180万円。月々にすると15万円です。そこに配偶者の収入が毎月10万あると合計で25万になります。

妻が正社員でバリバリ働いていると、夫の死亡保障はいらない場合もあるよ。
シングルマザーを想像するとわかりやすいかもしれません。遺族年金と金額は違いますが、シングルマザーの方は母子手当を受けながら生活をしています。
配偶者に収入と遺族年金があれば、一馬力でも生活ができます。そうなると死亡保障は不要となるのです。
とはいえ、世帯主が死んだときに保障がないのは微妙ですよね。死亡保障が必要な場合でもコスパよく準備する方法がありますので、こちらの記事をご参考にしてみてください。
現在、記事を編集中。近日公開予定
【介護のリスク】には公的介護保険
介護状態には公的介護保険という仕組みがあります。
しかし、40歳以上のみ対象です。
会社員、自営業者ともに40歳以上が対象です。

えー、若いとダメじゃん

そうだね。
若いと介護になっても国から保障ないよ
ざっくり公的介護保険の仕組み
介護給付を受けるには、要支援状態・要介護状態に認定される必要があります。
- 要支援1
- 要支援2
- 要介護1
- 要介護2
- 要介護3
- 要介護4
- 要介護5
介護給付は現金ではありません。サービスを1割の負担で利用できます。
公的介護保険の2つの区分と残念ポイント
公的介護保険保険は年齢によって違いがある
- 65歳以上が「第1号被保険者」
- 40歳以上65歳未満が「第2号被保険者」
交通事故は対象外の第2号被保険者
40歳から65歳未満のの第2号被保険者では、特定の疾病でしか介護認定がされません。なので、交通事故で介護状態になっても国からの保障は特にありません。
65歳以上の第1号被保険者は、介護になる理由は問われません。
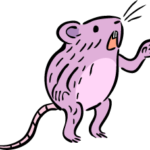
65歳までは交通事故でも介護保険はでないの?!特定の疾病って?

16種類だよ。
特定疾病は16種類です。
- 末期ガン
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靭帯骨格症骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病など)
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症脊柱管狭窄症
- 早老症(ウエルナー症候群)
- 多系統萎縮症糖尿病性神経障害
- 糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

そもそも40歳未満の人は、要介護認定は絶対されないということを知っておこう。
★コスパ★民間の介護保険の規定を確認
「要介護○以上が該当」の介護保険
40歳以上は要介護認定は絶対にされません。要介護1か要介護2以上という条件が主流です。3以上の介護保険は古いかも。
死亡保障または介護保障の保険
死亡保障と介護保障がセットになっている保険は保険料は高くなります。
加入している介護保険を確認してみよう。

「要介護2以上になったら」は注意。40歳未満はそもそも認定されませんよ。つまり該当しません。
小さく「または所定の要介護状態」と記載があるケースが多い。
その内容をよく調べてみると180日以上の寝たきり状態という会社がほとんどです。6ヶ月以上の寝たきり状態です。または所定の認知症が継続して90日以上といった感じです。

6ヶ月寝たきり・・。
該当するかな。。

今はもっと早い段階で該当する就業不能保険があるよ
介護保険に加入するなら、就業不能保険に上乗せする方が賢い入り方ですね。
介護保険、就業不能保険の違いってなに!?という方はコチラを参考に。
現在、記事を編集中。近日公開予定
【障害状態のリスク】には障害年金
病気やケガで障害状態になった時、要件を満たすと支給されます。
会社員、自営業者が対象となる障害基礎年金があり、会社員はさらに障害厚生年金があります。
障害等級によって受け取れる年金額も変わってきます。
障害等級表についてはこちらを参照してみてください。
1級の方が重い状態です。
障害等級1級
日常生活にも他人の介護を必要とする程度。常時介護を要する状態。
障害等級2級
日常生活に著しい制限を受ける程度の障害。
障害等級3級
労働するのが著しく困難で制限される状態。
注意
障害年金の障害等級と、障害者手帳の等級は別物です。管轄が違うので、それぞれの状態があります。
★コスパ★障害状態、就業不能、介護状態?
給付条件がよくわからない保険
それぞれ給付金の条件が異なります。障害に備える保険、就業不能に備える保険、介護に備える保険、、、全部ごちゃごちゃです。
保険商品の名前に厳密な決まりがなく、商品名だけでは区別できません。よく商品をしらべることで、重複や不要な保険にはいっている可能性があります。給付条件が該当しにくい保険にあえて加入する必要はありません。医療技術の進歩により、更に該当しずらくなる可能性があります。
【就業不能のリスク】には傷病手当金
就業不能とは働けない状態のことです。
就業不能のリスクには傷病手当金という制度があります。
これは会社員のみの制度で、自営業者にはありません。

えー!自営業の方が大変なのに!

自分で準備するしかないよ。
ざっくり傷病手当金の仕組み
連続して3日働けない状態で、合計で4日以上働けないことが条件
給付の条件に該当すると、給料の4分の3が支給されます。
支給される期間は1年6ヶ月です。
【保険節約ポイント】就業不能保険はバージョンアップが激しい
数年前に加入した就業不能保険
就業不能という名の保険が多発しています。就業不能の保険が登場してから数年しか経っていません。また、給付の条件が保険会社によって違います。
- 一定の就業不能期間を経過した場合
- 会社所定の状態になった場合
- 介護状態の場合
- 障害状態の場合
選ぶポイント
給付条件がどのタイプか?
○日以上の働けない状態(入院・在宅療養など)介護・障害状態と限定されている○○の病気で~~~と疾病が限定されている
「うつ」「妊娠・出産関係」は特別扱いされている場合もあります。気になる方は、確認しておいたほいがいいですね。
【病気・ケガのリスク】には健康保険
健康保険が一番なじみのある制度ですよね。
医療費は3割
病院にいった際に、窓口出払う金額は医療費の3割です。
つまり、7割が健康保険ということです。
ポイント
- 0歳から小学校入学前までは2割
- 70歳以上75歳未満は、2割(現役並み所得者は3割)
- 75歳以上は、健保から外れ後期高齢者医療制度となり、窓口負担は1割になります。(現役並み所得者は2割)
高額療養費制度
1ヶ月あたりの上限を超えると払い戻し窓口の負担が3割とはいっても、医療費が大きいと負担になります。100万の3割は30万のなのでかなりの出費です。
一定の金額を超えた部分が払い戻される制度が高額療養費制度です。
「一定の金額」は年齢・収入によって違います。
標準報酬月額が83万以上 25万2600円+(医療費ー84万2000円)×1%
標準報酬月額が53万~79万 16万7400円+(医療費ー55万8000円)×1%
標準報酬月額が28万~53万 8万100円+(医療費ー26万7000円)×1%
標準報酬月額が26万以下 5万7600万
低所得者 3万5400円

計算すると、太字の部分に数百円が加わる感じです。
標準報酬月額とは、4~6月の平均で以下のものが含まれてます。
- 基本給
- 役付手当
- 通勤手当
- 残業手当
【保険節約ポイント】高額療養費制度
高額療養費制度があるので、必要以上に医療保険を手厚くしなくても大丈夫。
病気によっても1日の負担額が変わってきます。
医療費がどれぐらいかかるのか、どれぐらいあれば足りるのかを把握して、保険を選びましょう。
医療保険がどのように変わってきたかを知ることも保険選びでは大切です。
詳細はこちら。

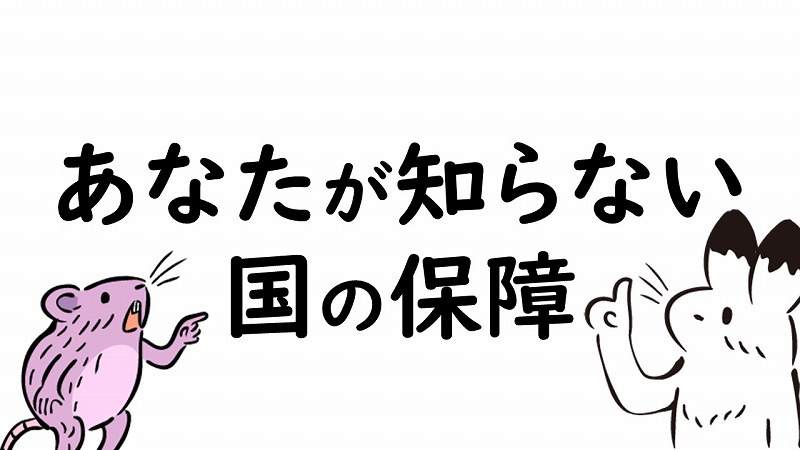

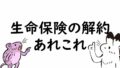
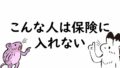
コメント